※物語の舞台のテニスコートでサーブ練習をする大地
【この物語の個人名、団体名等は仮名ですが、後は、ほぼ事実です。】
チューリップハットをかぶったその男性は、近づいてくるなりいきなり
「整列!」
と、叫んだ。大地を含めた体験入部生は皆ビクッとなり、慌てて4列横隊になった。
「きびきびした動きは若者らしくていいぞぉ。ようこそ柳田高校のテニス部に。歓迎します。」
「テニス部監督の木田です。よろしく。」
と、ほほ笑んだ。
大地は、強豪高校だから鬼監督と思っていのたが、案外優しそうだなと思った。
「今から、大体のレベルに別れてストロークをしてもらおうと思います。部員にボレーで返球させるので、思いっきり打ち込んでいいでーす。」
「現在やってる者はAコート」
「少し経験がある者はB」
「自信がない者はC」
「全くの初心者はDです。各自の判断で別れてくださーい。」
との指示に従い、大地はBの列に並んだ。すると横から父の宏之が
「監督、息子は足の大けががやっと治ったので、Cコートにしてください。」
と木田監督に伝えた。監督は、ニコニコしながら
「いいですよ。どうぞ。移動して。」
と承諾した。大地はしぶしぶC コートに移動したが、内心はBで自分の力を試したかった。CとDには初心者らしい女子生徒がいたのでなおさらそう思った。
だが、激しく動くとまだ傷口が引っ張られる感覚があるのでしょうがなく父の指示に従った。
いよいよ大地のストロークの番になった。10球程度で交代するシステムだ。飛んで来る一球、一球をていねいに打ち返した。
Wilsonの黄色のウエアを着て、赤いヨネックスのラケットを持った部員が笑顔で丁寧に返球してくれていた。ボールは全部大地の足元にゆっくり山なりに落ちてきて、非常に打ちやすい。どんな球でも同じポイントに確実に返球してくるボレーの技術に驚いた。
その部員は返球しながら大声で、
「うあー。すごーい。」「しびれるー。」「やるねー。」「ナイスショット!」
などの掛け声をかけてくれる。大地はそのお陰で、気分良くボールを打つことができた。
見学の部員が、
「Cコートの白いシャツの子、結構上手くないか?」
と、大地を指さして話している。
それもそのはず、Cグループには初心者や、超初心者の女子がいて、打ったボールはボレーヤーに届かなかったり、大ホームランになったりするような者ばかりいる。その中では大地はとても上手に見えるのだ。
Dコートでは、部員がボールを手で垂直に落下させ、打たせる練習をしていた。生まれて初めてラケットを持ったくらいのレベルに合わせての練習だ。
家族は、バックネット裏の木陰で大地の様子を見守っていた。太陽が南中し、一段と日差しが強くなった。近くにいた保護者が周りに氷を配っていた。弟の勇人と妹の鈴は氷を舐めながら兄の様子を見ていた。特に、勇人は、このコートで繰り広げられている全てに興味があり、あっちこっちに移動しながら、食い入るような眼差しで練習風景を観察していた。
AとBではドリル練習が始まった。球をロング・ショート・ショート・ロングの4か所に出して打つ。前後左右に振られるので、体験部員はバランスを崩す者がいたが、部員はいとも簡単にその4球をフルスイングでコート内に叩き込んでいた。体験部員と比較してボールのスピードが全然違う。息も全く乱れていない。
15分の休憩の後Aコートでは、ダブルスの試合が始まった。部員と体験部員のペア同士の試合だ。腕に自慢の体験部員と、現役の部員の球にはスピードがある。試合の中でサーブ&ボレー、トップスピンロブ、ドロップショット、ポーチ、スマッシュなど多彩な攻撃が繰り広がられらていた。
体験部員はそれを見学し、一球一球に歓声をあげながら応援した。
丁度そのころ、レギュラーメンバー10名が遠征試合から帰り、監督と話していた。
大地は、今までレギュラーがいなかったことに初めて気が付いた。控え選手でもあれほど上手いのに、レギュラーならどれだけ凄いのだろうと思った。
2時間位経過したころ体験入部が終わった。
整列した体験部員を前にして木田監督が
「どうでしたか。楽しかったですか。受験勉強に疲れたら、また遊びに来てください。」
と言った。
いきなり目の前の大地に
「お前、どっから来たんだ?」
「山口県です。」
「なんだぁすぐ隣じゃないか。また来い!来週また遊びに来いよ。」
と、すぐ隣り町から来るようなニュアンスだ。大地は
「是非、お願いします。」
と答えた。
こうして、大地の柳田高校テニス部の体験入部は終わった。
大地は、この高校に入り、テニスをしたいという気持ちがさらに高まっていた。
- 投稿者プロフィール
- かたさぶろう
最新の投稿
-
2020.3.18 シャイン もう一つのベイビーステップ【第11話】悲壮
-
2020.3.11 日本が誇る最高のテニスメーカー~メイド・イン・ジャパン・スピリット~
-
2020.3.8 テニスを上達させるための7つの方法
-
2020.3.3 「テニスウエアの革命」7人の勇者
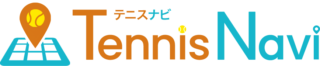




コメントを投稿するにはログインしてください。